 道すじ (1) 道すじ (1)この欄をかりて、私の生きた八十一年間を、ふりかえるとする。 ふるさとは、富士山より遠いところで、北アルプス北端の山、白馬岳・シロウマダケの麓。地元ではハクバサンと呼ぶ。そこから北へ、日本海にのぞむ糸魚川・イトイガワ平野まで深い谷がつづく。その谷が小谷村・オタリムラ・ふるさと。 小学校に入学するときに、父さんは私をリヤカーにのっけていった。2年生の私の綴り方を母がとっておいてくれ、それに次のようにある。「学校から帰ると、今日もトウサンがおごせていた」。心臓弁膜症の痛みに悩む父の姿を、方言で書いたものだ。母は、七男一女を育てて、九十七歳まで生きてくれた。村の谷底には、姫川と鉄道と県道が並んで走っている。生家は、鉄道と県道の間にあった。 小学二年の夏、父は他界した。この年の三月、私は免状をもらう役目を学校でやらされた。これは、四年生でもやった。 各学年は二クラスで、東組・西組が一年おきに担当したのである。 父の若死は、わが家を貧しいものにした。私は小学校を通じて新聞配達をして、家計を助けた。学校を出る時、用務員室においてあった60部ほどの新聞をもった。家に帰って配達順にしたものを紐で肩にぶら下げた。 カット:白馬三山 |
|
道すじ (2) |
 道すじ (3) 道すじ (3)小谷・オタリ村の谷底を走るJR線が、全通するまでに25年もかかったのは、村の北側の谷がけわしく、トンネルに次ぐトンネルの工事が必要だったから。さらに、太平洋戦争による工事中断もあった。村の人たちが日本海の海岸に出るためには、谷底の道を歩いて行くか、JR線で松本市・長野市を通って、新潟県の直江津市まで行くしかなかった。私の小学6年の修学旅行は二泊三日だったが行先は直線距離50㌔足らずの、隣の県の直江津市だったのは、そんな理由からである。それでも、生まれて初めて見た海の姿に、私は言葉を出すこともできなかった。 1泊目の長野市で、善光寺を中心とした都市の大きさに目を奪われたがこの町の人口は今でも40万ほどである。後に群馬県との境の碓井峠で関東平野をのぞむ空を前にして、この広さが空なんだと感動した。ひとくちに田舎・イナカというが、ふるさとの田舎っぽさをどう表現してよいかわからない。当時、北安曇・きたあずみ郡にただ一つの町・現大町市の旧制中学に入ったとき、クラスに集った各村々でよりすぐられた秀才の面々に、おそれ心をいだいた。 それでも、4年間、100人中の10番以内に入っていたのは、母親のDNAによるものと思う。 (写真:オタリ村の地形) |
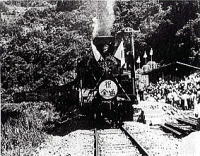
道すじ (4) |
 道すじ (5) 道すじ (5)小学校の六年間を通して、私にとって友達といえるのは一人しかない。性格が内気だったこともあろうが、毎日学校から帰ると、すぐに新聞配りに一時間あまりを使ったから。友達づきあいの時間がなかった。 一人でいるときは、子供ながらに、もの思いにふけることが多かった。残った二部ほどの新聞をもちながら、部落から部落への細い林みちを歩いていると、いろいろなことを考えた。 落葉をふむ音を聞きながら、心の中を探った。自分はどうして貧乏な家に生まれたのだろうか、どうして毎日、新聞を配らなければならないのか。答えの出ないことを、あれこれ思いあぐねた。 六年生の年の暮れ、なぜか私は友達の家にいた。コタツには、彼の姉もいた。三つ上で、松本の実践女学校へ下宿しながら通っていた。三人の兄たちと同じように、中学へは上れないだろうという私に、彼の姉は語った。 松本には、新聞配達の金で、中学へ通っている子もいるよ、と。 家に帰って、母にそんな話をしたら、汽車で大町の中学へ行けという。三人の兄たちの仕送りでなんとかなる、というのだ。私の人生を変えたのは3人の兄たちの力だ。人生って、わからないものだ。 (写真:南小谷小学校校舎) |
|
道すじ (6) |
 道すじ (7) 道すじ (7)小学校時代の思い出のトップは修学旅行だ。六年生の春。二クラス百人ほどの団体旅行。ルートは大町・松本・長野、新潟に入って直江津。 乗物は汽車。直江津の町に近づいたとき、汽車の窓に海が見えてきた。 「あっ、海だ、海だ」と思わず叫び声をあげたとき、周りの乗客から笑い声がもれた。私の叫び声が、よっぽどすっとんきょうだったのか。 海岸に立ったときの、体がふるえるような感動は、今でもよみがえってくる。これが海なんだという、おどろき。小谷村の深い谷底に育った人間には、見たこともないような雄大な海が、体ごと包み込んでくるような思いだった。 長野市に宿をとり街を歩いたときも、都会というのはこういうものなんだと、小谷村の小ささを思い知らされた。旅というのは、心の底から自分自身をゆるがされる。 善光寺の建物の大きさも、私にとって大きなおどろきだった。村にいくつかあるお寺が、私にとっての大きな建物だったのだから。 今だったらわかるが、長野市もそんなに大きな町ではないんだ。 小学校時代の思い出をたぐると、ふるさと小谷村がどんなに小さな世界だったのかわかってくる。まわりの人々の顔を思い出しても、一人一人はっきりしているほど、子供のころの社会は小さかった。 写真:千国・諏訪神社(小谷村) |
| 道すじ (8) 父の職業は、ロクロ屋だった。村で二軒しかなかった。父はロクロをモーターで廻したが、もう一軒は足で廻していた。 適当な材木を小さくきざんで、ロクロの回転板にとりつける。手もとに持った独特のノミを、回転する木片にあてると少しずつ削られて、父の考えているような形に出来上がっていく。かたいケヤキの枝で茶盆を作ったり、注文に応じていろいろな器を作っていた。 二番目の兄は、父のロクロを継いだ。ありきたりの器(ウツワ)だけでなく、新しい形のものを作り出した。そんな時は、仕事場のロクロの前に長い時間すわりこんでいた。こっそり、隣の部屋からのぞいていると、ときどき出来上がった品物を、回転板からはずして、遠くへ投げつけていた。こういうのを職人気質というのだろうか。だけど、こんな仕事を続けていては、利益は出ない。 だから、注文の多い品物も力を入れて作っていた。私は製品をまとめて 日用品を売っている店へ持っていった。その程度の手伝いで、家の収入に貢献できない。そればかりか、学費を出してもらっている身が、兄たちに対して気が引けた。 こういうのを、甘えているというのだろう。 |
|
 ロクロ工房内部 |
 工房のノミ ノミは製品に合わせて自作した。 |
| 道すじ (9) 兄たち三人は家を離れていたから、小学校時代の私は弟・妹たちの兄という立場だった。 その頃に、二人の面倒を見た、という記憶はない。兄たちから目を向けられないという、その自由さが気持ちを楽にさせたのか。そんな気分からオレが兄なんだと、弟たちに威張っていたように思う。自分が思うように生きていけばいいというそんな生き方だった。 ひとりよがりの私をとっちめてくれたのは中学への進学だった。北安曇(あずみ)郡の町村の小学校から選(よ)りすぐられて集まったのだから、私に劣等感を抱かせる人物が多かった。その頃の私は、自分に閉じこもるタイプだったから、友人をつくることが出来なかった。自分ひとりの心を持て余して、教室に座りながら、教科書を読みふけった。 小学校の読本(とくほん)と違って、中学校の本は一流作家の文章で埋まっていたから、私の知識欲を大いに満たしてくれた。中学校の先生の中には、教科書の内容から離れて人生経験を語る人が何人もいた。そんな時は、机の椅子に身をかたくするように座って、先生の話に聞き入った。 黒板をうまく使って話す先生には、とくに引き寄せられた。 |
|
 |
 昭和8年 文部省編 国定第4期国語教科書 通称『サクラ読本』 写真提供:京都市学校歴史博物館 |
 道すじ (10) 道すじ (10)父が40代で亡くなったことで、家計の重荷は母の両肩にかかることになった。 兄たち三人は、つぎつぎと出稼ぎにいったが、その仕送りだけでは家計は成り立たなかった。母は行商をはじめた。初めは反物(たんもの)だったが、次に駄菓子になった。背中からはみ出す大きさの箱に売り物を入れて、部落から部落を売り歩いた。ルートは私の新聞配達のルートと重なった。箱に入った駄菓子をときどき盗み食いしたことを覚えている。子供の足で一時間のところを、これはという家々に寄りながら、重い荷を背負いながらの行商だった。 私は新聞配達から帰ると、米を研いで飯を炊き味噌汁をつくり、漬物を刻んで夕飯の支度をした母の帰る時間を見計らって、提灯(ちょうちん)をつけて迎えに出かけた。弟妹を供にすることもあった。 こんな生活を、小学生の友だちと比べることはしなかった。大町中学へ行かせてもらうことだけで、私は幸せだった。 私は、母の購読していた夫人倶楽部の付録を読んでマッサージを自習した。練習台は母の体である。ウデは次第に上がって、効果は母が認めてくれた。体中のツボは今でも指が覚えている。 このように、目的は何であれ、新しい技術を身に付けることは、今でも私の好きなことである。 ※写真:行商の行李(こうり) |
 道すじ(11) 道すじ(11)青春時代のなかで、強く印象に残っているのは旧制中学校の4年間である。 1941年、太平洋戦争がはじまった。中学校に入った年で、同級生のなかの何人かは、土浦海軍航空隊に入隊した。少年兵である。 中学校では汽車通学生と呼ばれた。女学校でも同じである。大町駅を降りた男女は、それぞれ隊列を作って中学校・女学校へ向かった。中学校のグランドの前には、連峰の雄大な姿がデンとかまえていたことが、強く印象に残っている。 英語担当の教師は陸軍将校だった。戦争の記念日に軍服を着て来たのを覚えている。絵画担当の教師は美術学校の卒業だった。授業時間内にくり広げられる美術論は、私の心をとらえた。 小学校と中学校の授業の違いは大きかった。中学校での日々は、知識欲を刺激した。歴史の授業担当の教師にも、心をひかれた。 文法(ぶんぽう)という授業もあった。週一回の授業の始めには、必ず答案用紙を配った。それに、アイウエオを書かせる。五十音が文章の基礎だと、いやというほどに教え込まれた。 美術の教師の話は、絵を描く私の心に、今も残っている。 ※写真:爺ヶ岳とそのふもとに広がる大町市(写真提供:大町市観光協会) |
 道すじ(12) 道すじ(12)中学校の4年間を通して、勤労奉仕という作業があった。 町にあった工場の手伝いとしては、中学校は昭和電工、女学校は紡績工場だった。学生も戦争に協力すべしという、国の方針だった。配置された職場は、電気分解に使う電極を作る。高さが大人の肩ぐらいの四角柱は、石炭の粉を電気で固めるもの。1日の作業が終わるころは、鼻の穴がまっ黒になった。若い男は軍隊にとられて、どこの職場でも人手が不足していたのだ。 学校に行く日が少ないから、教科書を消化する時間も少なかった。それでも、いくばくの知識を吸収できたのは、級友同士が刺激しあっていたからだと思う。英語がすぐれた友、数学にすぐれた友、なんでもできたトップクラスの友。この年齢になってもその顔が浮かんでくる。汽車通学では上級生がすぐそばにいたから、大人と触れ合うような感化を受けた。もちろん、コワイ面もあったが。汽車には一般の乗客もいた。おお、お前はあそこの息子か、と声を掛けられると、大人びた気分にさせられた。 通学生仲間の会話としては、女学生のウワサをする時が、一番もりあがった。女学生の間で、中学生をウワサしていたことは大人になって知った ※写真:勤労奉仕に向かう学生(写真提供:愛知県立犬山高校) |
 道すじ(13) 道すじ(13)中学1年の年に、学校創立70周年の記念行事があった。その一つに絵画展示会があり、各学年を代表する絵が玄関ホールに飾られた。1年代表の私の絵は、小谷村の平凡な田舎風景だった。 人間はほめられると、一生懸命やると言われるが、私の絵心はこの展示会に火をつけられたと言ってよい。絵の授業に熱中するばかりではなくて家にいて暇をみつけては絵を描くクセがついてしまい、80歳の今におよんでいる。 田舎のわが家の隣に住んでいた、私より5つ年上の男の人が絵を描いていた影響を受けて、スケッチ旅行にあちこち連れて行ってもらった。千葉県の銚子の風景が気に入った。その人の小学校の同級生が美術学校(今の芸大)を出ていて、東京の上野公園内の建物で開かれる絵画展に出品していた。私はその人の手ほどきを受け、2、3年後には、同展に出すようになった。絵の大きさはたたみ半畳ほどで、それまでのスケッチブックの絵よりも高い技術が要求され、描く時間も長くなり私は絵の虜になった。 今までに大小とりまぜて数百枚の絵を描いている。知人にすすめられて個展も開くようになった。 最初は上吉田の喫茶店アーヴェントだった。同店の社長のすすめもあってのことーー。 ※写真:アーヴェント |
 道すじ (14) 道すじ (14)中学校全体の作文集というのがあった。年一回の発行である。 二年のとき、作文の時間に書いたものが選ばれた。学校全体が参加する登山についての作文である。学友たちの書くものは、たぶん白馬岳の麓から出発して、山頂までのことを書くに違いない。 ちょっと変わった趣向でと、『山頂』と題した。このもくろみが当たって代表に選ばれた。 山頂に着いたのは、午後の遅い時間だった。夕食までの自由時間に、山小屋の前に立って、まわりを見ての写生文。山の東側は切り立った崖で、雲のかたまりが足もとに並んだ。西側は日本海だが、雲の連なりだけが続く。太陽を隠した、うす明るい雲は、平地では見ることのできない景観だった。逆光で見ているから、雲の頂きは明るいが下へ行くほど黒い雲のかたまりが続く。「まさに雲海という絶景である」と書いた。 小高い岩の上に、若い女性が立っていた。下からカメラをかまえる男の人の姿が見えた。髪を風になびかせている様は、まさに絵のようである。 「ローレライの魔女を想像した」の文には、赤い傍線が引かれていた。いま思い出しても、カッコウ良い文章を綴ったものである。文集の中でも、評判のよいものとなった。 ※写真:白馬岳山頂と白馬山荘 (写真提供・著作権保持:白馬村観光局) |

道すじ (15) |
 道すじ (16) 道すじ (16)中学四年の同級生が、何人も軍隊の学校に入った。陸軍予科士官学校に二人、海軍兵学校に一人海軍機関学校に一人。土浦海軍航空隊には、二年生のとき、何人かの同級生が入った。 士官学校は、埼玉県の朝霞町(現在は市)にあった。全国から数百人ほど入ったと思う。一つの部屋にベッドが六台あり一つは上級生で、生活全般の指導に当たった。 校舎は中隊単位で、一年二年がそれぞれ百人ほどだった。午前中は学科で、中隊ごとに隊を組んで教室棟に向かった。午後は軍隊訓練である。中隊ごとに専属の下士官が指導に当たった。 学科は現在の高校程度だったが、教官は優秀な人がそろっていて、生徒の向学心を満足させる内容だった。高等数学では微分・積分を教えていたから、終戦で故郷の高等学校に入ったとき、士官学校での授業内容が高度だったことがわかった。 各部屋の入口には、各人の歩兵銃が並べて置かれ、ていねいに手入れするよう、厳しく指導された。銃に個人の人格が反映する、というような指導であった。 終戦で家に帰ったときに、兄たち召集兵の軍隊とは大きく違うことがわかった。 私にとっては、軍隊教育は役立つ内容だった。 ※写真:朝霞市基地跡地の航空写真 (写真提供・朝霞市) |
 道すじ (17) 道すじ (17)昭和二十年、終戦の年の二月から八月まで、軍隊の経験をした。陸軍予科士官学校である。 生涯に一度の経験であったが、記憶に強く残っている。いくつかのことを記す。 馬事訓練。生徒一人に一頭の馬。専門の下士官が付いてくれた。馬の鞍に右手をかけ、左手でタテガミをつかむ。ひとつかみの毛を手に巻きつけ左足をあぶみにかけて、エイ、ヤッとばかりに自分の頭よりも高い鞍に上がる。自分の重みが全部かかるから、タテガミを引かれて馬は痛いのではないか。そんな思いが頭をかすめた瞬間、左手からタテガミが抜けた。アッという間に、馬の腹の下に仰向けに倒れた。 オイッ、馬が笑っているぞ、と下士官に怒鳴られた。やり直して、無事あがった馬の鞍は高かった。その位置に身体を預けて、揺られていくのだから、怖い。けれども馬はこちらの気持ちがわかるのか、柔らかに歩いていく。選りすぐられた良馬だと下士官に説明され安心して乗ることができた。校内で慣れると外の道路を馬は歩いていく。目の高さは道路から三メートルもあるから、慣れてくると爽快な気分になった。軽いかけ足の馬の背から、周りの景色を眺めるのはこの上ない気持ち良さであった。 ※写真:今も残る陸軍馬事訓練所跡 ((写真提供:北海道登別市)) |
 道すじ(18) 道すじ(18)陸軍予科士官学校のこと(続) 昭和二十年二月、入学したときに映画を見せられた。士官学校の概要を教えるためのもの。 初めのシーン。軍服を着た学生が整列した前で陸軍中将が演説をした。「士官学校とは、死ぬことを教える学校である」。 あまりにはげしい言葉であるが、これを具体的に教えられたことは、いま覚えていない。埼玉県の、武蔵野の原っぱに整列したが、不動の姿勢をとらされているのに、激しい風にさらされて、身体が動いた。 実弾射撃訓練は、この原っぱで行われた。腹ばいになり、両ひじを立てて銃をかまえる。繰り返し訓練されてきたことだが、実弾だと思うと、身体が固くなる。腹ばいになり、銃の照準孔を通して、的の二重丸を狙う。微妙に銃が揺れて、教えられたとおり、息を止める。引き金にかけた右手の人さし指を、ゆっくり動かす。バーンという音よりも先に、銃の台じりが右肩に衝撃を与える。 タマが的に当たったかどうか、目では確かめようがない。小さな旗を振って、何かを知らされたのだが、よくは覚えていない。 数少ない体験だが、今でも身体にショックが残っている気がする。鉄砲打ちは、こんな体験を繰り返しているのだなあ。 ※写真:防衛省ホームページより |

道すじ (19) |
 道すじ(20) 道すじ(20)終戦(しゅうせん)という日は、不思議な感動をおぼえる日である。昭和二十年八月十五日。 いま、その時のことを思い出そうとしているのに、これといった情景がよみがえってこない。 「戦争は終わったんだよ」と、中隊長のはっきりした言葉があったかどうかまったく記憶にない。 あの日に、何がどうなったんだろうか。いまわずかに記憶に残っているのは、背嚢(はいのう)をランドセルのように背負い、冬服一着と下着のひと揃いに、軍隊へ家から持っていった漢和辞典を入れて帰った。 「転入学」ということがあった。軍隊の学校と一般の高等学校、専門学校とが、同等であると認められたのであった。ところが、別の難関が待ちかまえていた。食糧事情である。自宅から通学するという条件を満足しなければならない。一番近いところで松本高校だったから、通学不能でだめだった。翌年三月の入学試験を待つしかない。 そんな時、どこで始まったというのではないが各神社の祭りを若い者で盛り上げようという気運が、各部落に広まった。素人芝居をやるところが多く、仲間が寄り集まって色んな工夫をして、実演にとりかかったものである。 ※写真:終戦 |
 道すじ (21) 道すじ (21)昭和二十一年、村で弁論大会があった。私の部落でも、代表を決めようという動きがあり、小さな社(やしろ)の建物に若い者が寄り合った。 私は、戦争が終わって平和な時代が始まるときに、若い者はどうしたら良いのか、というようなことをしゃべったと記憶している。 それが、村の代表のひとりに選ばれる結果となった。大町に集められたものの中から、郡の代表のひとりとなった。長野市の大会で、3位か4位になったと思う。 この年の夏、上級学校へ進んだ。母が新聞で見つけたもので、逓信省設立により、学費がいらないばかりか月々給料をくれるという。幹部養成学校だったのである。当然卒業したら逓信省に勤めるという約束である。 この学校も全国から応募者が集まった。全員入寮する条件で、学校の場所は埼玉県。私が入っていた陸軍予科士官学校の校舎が使われたので、なつかしい思いで毎日を過ごした。 中学時代の私に友人が少なかったが、ここでも多くの友人はもてなかった。それでも、北海道・大阪・広島の友達ができた。それは、逓信省をやめた後も続く、長いつきあいとなった。 ※写真:逓信省(国立国会図書館より提供) |
 道すじ (22) 道すじ (22)終戦の翌年に私が入った学校は、高等逓信講習所という名前だった。私の生涯を通じての職業となる電信電話業務、その基本となることを教えるところだった。 教科の内容は、電話と電信の二つに分かれていて、私は電話の方の技術部門を選んだ。はじめの半年は、専門ではなく普通学科であった。そのなかに、いま八十歳過ぎでも記憶に残る先生が、何人もいる。東京大学に籍を置きながら、私たちの学校の先生となった人がいた。受持ちの学科は覚えていないが、週一時間の授業は強烈なインパクトを与えるものだった。 ゲーテ、ヘルマン・ヘッセという、初めて聞く小説家の名前を挙げながら、しゃべる内容は私の心をわしづかみにした。私は親しい友人の案内で東京・神田の古本屋街へ足しげく通った。先生に教えられた小説の、古本を買い求めるために…。 買った小説に心をうばわれ、私は肝心の学科を勉強するのを忘れてしまった。当然の結果として卒業のとき、百五十人中の百四十五番だった。 今でもヘッセの小説を読みふけった日々のことは、なつかしくよみがえってくる。 ああ! 青春! ※写真:ヘルマン・ヘッセ |
 道すじ (23) 道すじ (23)電話局づとめの第一歩は、横浜の鶴見局であった。東京・目黒区の伯父の家から通った。講習所に入る前も、下宿住まいしていたところだ。自由ヶ丘から東急電鉄で蒲田乗り換え、JR京浜東北線である。 今の時代では考えられないが、電話のついていない世帯の方が多い状態だった。事務用電話が住宅用に優先していたから電話局の職員に頼んで、少しでも早く…という風潮だった。コネというのは、いつの時代にもあろうが、当然の人間の心理なのかもしれない。ヨソモノの私には、頼む人もいないから、その点は気軽だった。 電話の申し込み事務の課に、目立つ美人が2人いた。その1人に私は心を奪われていったのは、青春の心理の自然な動きであろう。恋愛経験のなかった私には、良い結果は得られずに終わった。 転勤するまでの8年間は、長かった。後の4年は市の全体の電話を統括していて、そこの技術部門に4年いた。 そんな私の青春時代というのは、焦りの時代と言っていいだろう。 技術の知識を生かす場面がないといってよいから、さらに上の段階に転勤するチャンスをうかがっていた。 ※写真:今や貴重な黒電話 |
 道すじ (24) 道すじ (24)昭和30年代の日本は、高度成長期へ入っていく頃であった。それは、私にとっても発展の始まりであった。 NTT本社へ転勤を命じられ、施設局という部門の勤務となった。施設局長は後に副総裁から総裁になった北原安定という人だった。担当した仕事は、道路通信という新しい分野である。高速道路の建設が始まったばかりで、道路公団も組織がまだ新しかった。名神高速道路が開通して1年、名古屋~東京間の高速道路の建設が始まった。 インターチェンジ(I C)という言葉が真新しく、私の頭に具体的なイメージをつくっていなかった。公団の通信課へ、足しげく通ったが、新しい道路通信という分野がNTTの組織の中に出来たのは、何年も後のことである。名神の道路通信は、すでに公団の手で作られていた。道路の中央分離帯の中に、通信ケーブルが埋められていた。 事態がそのまま進んでいけば、日本中の道路通信を公団が運営することになる。それは困る。 なぜか。法律で、国内の通信は電電公社が一元的に運営することに決められていたからだ。「東名以降の高速道路の通信は、NTTが建設し運営する」ことに、国の施策が決定した。 ※イメージ:高度経済成長と歩調を合わせた高速道路網整備 |
 道すじ (25) 道すじ (25)昭和30年代は、日本の発展期である。私もNTTに勤めて、発展をはじめた。横浜から上部段階に転勤したのである。電話局は各県ごとにグループにまとめられ、運営されていた。各県はさらに、地方ごとにまとめられた。東京は巨大だから一地方となり、その他の県と山梨を含めたものが、関東地方となった。関東をまとめる官庁は東京の大手町にビルをかまえた。そのビルへ、私は昭和30年に転勤した。 全国を10地方といて、全体をまとめる本社が東京の日比谷にビルをつくった。私はそこへ、昭和32年に転勤した。本社勤めの社員は、当然のこととして全国へ出張する機会が多かった。私も、大手町時代は関東一円に出張し、本社時代は全国へ出張した。 本社へ移って3年後、新しい仕事を命じられたのである。高速道路の通信という分野だった。 当時、神戸から名古屋の名神高速があり、その通信は道路公団が運営していた。そのまま、全国に拡大されては困る。法律で、通信はNTTが一元的に管理すると決められていたからだ。 ※(写真)大手町にあるNTTコミュニケーションズのビル |
 道すじ (26) 道すじ (26)昭和30年代の日本の社会は、発展の時期であった。NTT本社に移った私にとっても、発展の始まりだった。 担当した仕事は道路通信である。当時、名神高速道路ができて、東名高速道路が名古屋から始まっていた。名神の道路通信は、道路公団が運営していた。東名以降の道路通信をNTTが運営するためには、公団が運営している通信事業の内容をつかむ必要がある。 私は、せっせと公団の通信課へ通った。東名の道路通信をどんな設備をつかってやろうとしているか、それを探るのが仕事だった。2、3ヶ月を過ぎて、NTTと公団の両総裁が昼食をともにする席が設けられ、話が決まったのである。私の仕事が終わり、次のポストに転勤した。関東支社の課長である。 そこに2年いて、次は通信研究所、通研と呼ばれていた所に移った。そこの電話機研究室の室長補佐だった。仕事の内容は特に決まっていなくて時間を持て余していた。 ある日、室長がにこにこしながら、新しい研究テーマが決まったと話した。「小型電話機」である。今は社会のどこへ行っても見られるそれを、新しく作り出す研究が始まったのである。 ※写真:1980年代に登場した「ショルダーフォン」(画像提供:NTTドコモ) |
 道すじ (27) 道すじ (27)電話機研究室には、研究者が十数人いた。送話器、受話器、ベル、コードなどの各部分を、各人が担当していた。 たとえばベルをとってみると、ベルの専門家から見ても全く新しい別のものを開発することになったのである。新しいといっても手本はあった。米国の会社ベルがつくった小型電話機を数台購入し、それを分解したものを各研究者は手許に持った。研究者はそれぞれが担当するものについて、米国製の部品を精密に調べ、それに負けない新しいものを作り出さなければならない。私が転勤していったときには、試作品の設計図は完成していて、試作品の製造に着手していた。 通信研究所(通研)は設計までで、部品の製作はメーカーの研究陣が担当していた。彼等は通研に日参するのが仕事である。メーカーは、日本電気、日立電気、沖電気の大手のほかに、中小の各社があった。室長補佐の役割は、彼等の研究がスムーズに進んでいくようにすることである。 彼等が通研の敷地内にこもっているだけでは、ちょっとかわいそうだといいことを考え付いた。 NTTの各現場では、新しい研究をどのように受け入れるかを研究者が確かめにいくことだ。 ※1946年アメリカ 世界初の移動体電話 (画像提供:「昔は東通工」様」) |
 道すじ (28) 道すじ (28)通研の研究者をNTTの現場に引き出すために日本全国のあちこちへ出張させる計画は、彼らに好感をもって迎えられた 室長補佐の仕事の役割を、こんな話で理解していただけたろうか。 次の人事異動で、私は初めて電話局の局長に任ぜられた。神奈川県の座間市である。局の規模は中くらいである。 この街は、日本で唯一の在日米陸軍が駐留しているところである。とは言っても、NTTから見れば規模の大きい会社にすぎない。局長の立場から見て、特に難しい問題は何一つ起きなかった。 次の職場は、学園である。NTTの職員の能力を向上させるための、部内の学校といってよい。NTTの職種別に、グループ分けされていて、私は技術部長であった。数十人の教官をまとめる立場である。NTTの中でも、地味な職場と言ってよい。 私のNTT内の最後の職場は、富士吉田の電話局長であった。 私にとっては、富士山の麓の生活は生まれて初めてであり、貴重な体験となった。そして、ついには生涯の最後の時をすごす場所となった。そして、佐藤新聞店と縁ができた。同店発行の情報紙に、文章を連載することになったのである。 ※キャンプ座間の航空写真(画像:神奈川県HPより) |
 道すじ (29) 道すじ (29)この情報紙『ニュースCS』は、私が寄稿し始めたころは、『朝日だより』といっていた。コラム欄があって、富士吉田のことが書かれていたから、私は参考にとバックナンバーをもらいに佐藤新聞店(ニュースセンターサトー)へ行った。話は、私の寄稿の方へいってしまった。 「北麓漫歩」という題名にした。結局、何年分も続いて単行本を発刊する羽目になった。自費出版という初めての経験をした。書くことによって私の地元に対する興味は倍増した。調査もできるだけのことをした。 訪問するのが私のやり方で、取材先へいきなり出かけていって、色んなことを聞き出した。時には地元の人でも知らないようなことが書かれているよ、と言われたりもした。本の出版は、全く新しい経験であった。印刷所をさがし、表紙は自分の描いた絵の中から選んだ。自費出版だから、あちこちに売りに行かねばならない。図書館へも寄贈した。 そんなこんなで、私はこの土地にとけこんでゆくことができた。自分の人生が深くなったことを体験した。 書くということは、自分を見つめることだと知った。 ※写真:朝日だより(ニュースCSの前身) |

道すじ (30) |
 道すじ (31) 道すじ (31)自作の絵の個展を開くことになったのは、佐藤新聞店の前社長が言い出したことがはじまりである。上吉田の喫茶店、アーヴェントの社長がそれを受けて私にすすめた。会場はアーヴェントである。 出品する絵は、みんな額縁に入れなければならない。上吉田の額縁屋にたのんだ。絵の大小に応じて、30点を超えたろうか。苦労をかけた。当時の記録は、出品作の目録をはじめ、いっさい手元に残っていない。お世話になった関係者には、心からお礼を申し上げる。 当然、作者の私は期間中は会場につめた。全作品が手元から離れた。専門家でもない私の絵を、もとめて下さった方には感謝の言葉を言い表しようがない。 作品を描くには、北麓のあちこちに車で出かけた。スケッチの道具というのは、けっこう数多いものである。素人ながら白黒の素描から、色鉛筆や水彩、油彩からガッシュまであった。 画材は富士山が多かったが、近景を選ぶのにこだわった、誰も描いたことのない絵になったと思う。 ※写真:富士山の絵 |
 道すじ(32) 道すじ(32)絵の個展が終わってみると、完成感というか安心感のような気分に浸っていることに気付いた。誰と誰が見にきてくれたか、来場者が何人ぐらいになったのかが、気になっていた。大勢の人の目に、私の絵はどのように映ったのだろうか。 そう思うと同時に、確かに私の絵は全部売れたのだと安心できた。自分の作品が北麓のあちこちの、個人の方々の家に飾られていることは、想像の仕様がなかった。お前の絵があそこにあるよ、といわれて見に行ったのは、勝山村の体育館だった。ああ、公共の場のこんなところに飾ってくれたのだと、村の人々に心から感謝申し上げる。ある個人の方は、私の絵の中から五湖の絵を揃えてお店に飾ってくれた。感激である。 都留信用組合の前理事長の石原さんも、私の絵を自宅や勤め先に飾ってくださった。本当にありがとうございました。 私の中の満足感は虚脱に変わり、その後、絵を描いていない。(完) ※写真:富士山の絵 |